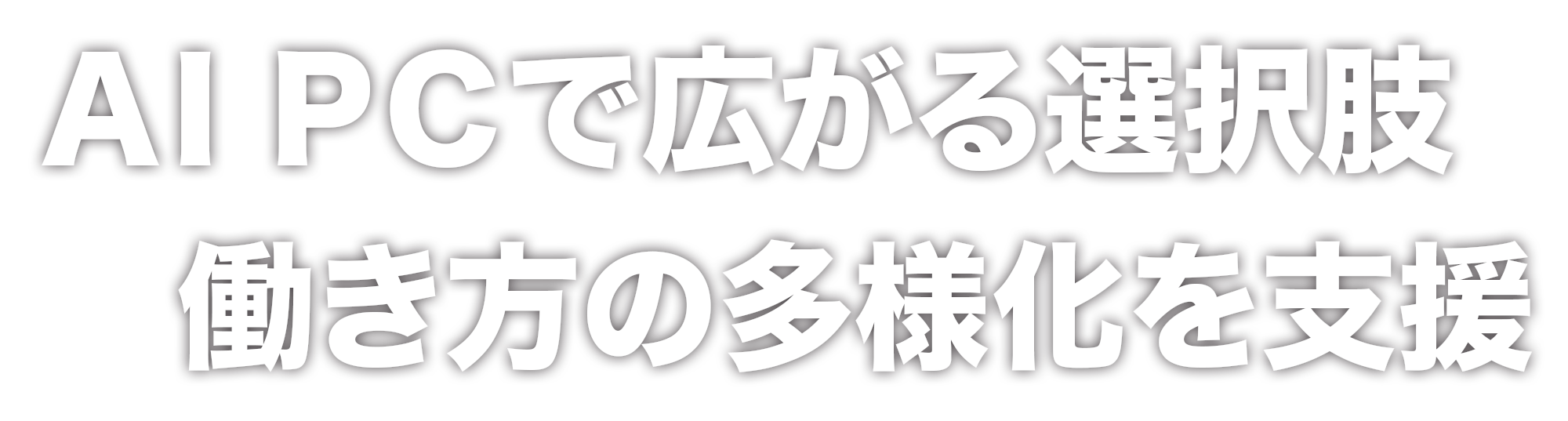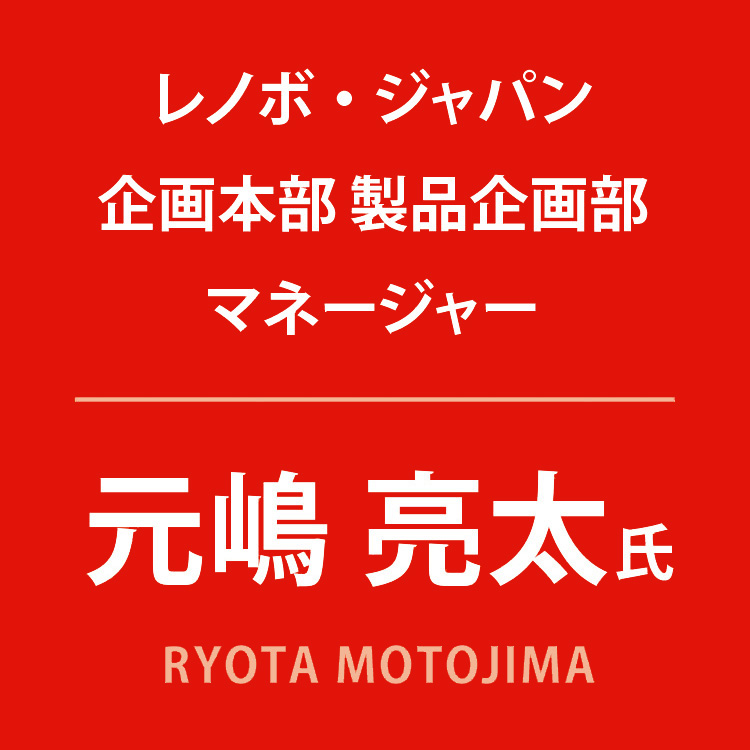非通信で情報保護
AI PCとは、どのようなパソコンなのか教えてください。
AI PCは端末がネットワークから切り離されたオフラインの状態でも人工知能(AI)を利用しやすい性能であることが特徴です。ローカルでのAI運用を前提とした性能とセキュリティーの担保が、一つの要件になるといえます。
ビジネスシーンでは、メールや議事録、プレゼン資料などの文書作成や情報収集の効率化を目的としたAI活用が増えています。
現状、その多くはクラウド型であり、データ処理の際にクラウドと通信します。一方で、PCの外で処理が実行されるため、コストや反応速度、ユーザー一人ひとりへの最適化の観点では、多くの課題も残されています。
AI PCはAI処理に特化したNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)と呼ばれるプロセッサーを内蔵しており、端末上でデータ処理を完結できるスペックを有します。PC上で処理を完結させることで、動作速度が通信環境に左右されず、AI利用時のセキュリティーも高いレベルで担保できます。
足元では働く場所を使い分けるハイブリッドワークの導入も進んでいます。様々な場所や用途でAIを利活用するうえで、AI PCは欠かせない存在といえます。
ビジネスにはどのような利便性をもたらすのでしょうか?
AIは利用者の行動や入力した情報を学習し、個々の特性に応じて調整されたデータベースを構築します。学習機会が多いほどAIの精度は向上するのです。
直近では入力内容を学習に使用しない企業向けのクラウド型のAIも増えてきました。加えて、ネットワークを介さず、端末内の稼働で完結するAI PCであれば、さらなる業務での使用制限の緩和が期待できます。
AIの個人への最適化が進めば、仕事に伴走してくれる、自分の脳をアウトソースした、分身のようなアシスタントを作れます。例えば、自分のPCの中にだけ存在する情報を基に情報をまとめたり、質問をすることができます。また、光学文字認識と組み合わせれば、画像や図表データの内容をAIが認識し、より高度な検索も実行可能です。
「AIが人の仕事を奪う」という意見もありますが、実際にはAIが人に代わり業務に携わることで、適材適所の人材配置が進むのではないかと考えています。少子高齢化が深刻化する昨今、人材不足は社会的な課題です。例えば、従来は手作業でやっていたデータ整理をAIが担うことで、限られた人的リソースをより高い付加価値を生む業務に振り分けられます。個人単位でも、単純作業から解放されることで、利益につながる本来業務の時間の確保や、ワークライフバランスの改善といったポジティブな影響が見込めます。
AI PCの登場もあり、AIは利用者にとって身近な存在になりつつあります。近い将来、個人に最適化されたAIは当たり前のものとなり、ユーザーを補助してくれる存在になるでしょう。
求められるスキルとは?